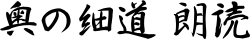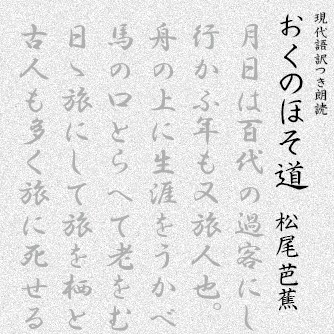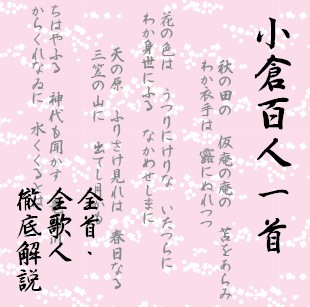大垣
■『おくのほそ道』の全現代語訳はこちら
■【古典・歴史】メールマガジン
■【古典・歴史】YOUTUBEチャンネル
露通(ろつう)も此(この)みなとまで出むかひて、みのゝ国へと伴ふ。駒にたすけられて大垣の庄に入ば、曾良も伊勢より来り合、越人(えつじん)も馬をとばせて、如行(じょこう)が家に入集る。前川子(ぜんせんし)・荊口父子(けいこうふし)、其外(そのほか)したしき人々日夜とぶらひて、蘇生のものにあふがごとく、且(かつ)悦び、且いたはる。旅の物うさもいまだやまざるに、長月六日になれば、伊勢の遷宮おがまんと、又舟にのりて、
蛤のふたみにわかれ行秋ぞ
大垣
現代語訳
路通もこの港まで迎えに出てきて、美濃の国へ同行してくれた。馬に乗って大垣の庄に入ると、曾良も伊勢から来て合流し、越人も馬を飛ばしてきて、如行の家に集合した。
前川子・荊口父子、その他の親しい人々が日夜訪問して、まるで死んで蘇った人に会うように、喜んだりいたわってくれたりした。
旅の疲れもまだ取れないままに、九月六日になったので、伊勢の遷宮を拝むため、また舟に乗って旅立つのだった。
蛤のふたみにわかれ行秋ぞ
(意味)離れがたい蛤のふたと身が別れていくように、お別れの時が来た。私は二見浦へ旅立っていく。もう秋も過ぎ去ろうとしている。
語句
露通 八十村路通。近江大津の人。もとは三井寺の学僧であったという。乞食放浪行脚の俳人。はじめ「奥の細道」の随行者に予定されていた。素行が悪く芭蕉の怒りを買ったこともあるが、後に許された。正しくは「路通」だが故意に字を変えている。 ■大垣 4.戸田氏定(とだうじさだ)十万石の城下町。現岐阜県大垣市。 芭蕉の大垣着は8月21日頃。芭蕉は『野ざらし紀行』の旅でも終盤に大垣を訪れて「しにもせぬ旅寝の果よ秋の暮」と詠んでいる。 ■越人 ■越智越人(おちえつじん)。名古屋の染物問屋。別号に槿花翁(きんかおう)。尾張蕉門の重鎮で、蕉門十哲の一人。元禄元年(1688年)「更級紀行」の旅に同行。 ■如行 近藤如行(こんどうじょこう)。通称源太夫。もと大垣藩士だが僧侶になる。 ■前川子 津田前川(つだぜんせん)。大垣藩士で大垣蕉門の一人。「子」は敬称。 ■>荊口 宮崎荊口(みやざきけいこう)。通称太左衛門。大垣藩士。此筋(しきん)・千川(せんきん)・文鳥(ぶんちょう)の三人の子とともに芭門に入る。 ■伊勢の遷宮 元禄2年(1689年)は伊勢の神宮の式年遷宮の年だった。内宮は9月10日、外宮が9月13日に行われた。伊勢神宮は皇大神宮(こうたいじんぐう・内宮ないくう)と豊受大神宮(とようけだいじんぐう・外宮げくう)を中心とした大小の社の総称。遷宮は二十年ごとに本殿改築の際にご神体を移す儀式のこと。40代天武天皇が定め、41代持統(じとう)天皇の4年(690)に始まる。 ■又舟にのりて 大垣船町の回船問屋谷木因宅前から乗船し、水門(すいもん)川・揖斐(いび)川・長良川を下り伊勢湾に出て伊勢の二見が浦から伊勢神宮へ向かった。千住の章の「舟に乗りて送る」「船をあがれば」に対応する。
解説
『おくのほそ道』結びの地、大垣です。芭蕉は当初旅のお供として予定していた八十村路通はじめ、伊勢から合流した曾良、越智越人、近藤如行、宮崎荊口など多くの門人にあたたかく迎えられます。
「先生、おかえりなさい。先生、おかえりなさい」
「みんなありがとう。ありがとうな」
和気藹々とした師と、弟子の場面が浮かぶじゃないですか。「蘇生の者にあうがごとく」…死んだものがよみがえったようだ。それくらい、喜んでくれたってことです。たいへんな、よろこびようですね。
大垣で一息ついた後、芭蕉は廻船問屋をいとなむ門人の谷朴因の家の前から舟に乗り、大垣市内を流れる水門川から揖斐川(いびがわ)へ。さらに長良川、伊勢湾に漕ぎ出し、伊勢の二見が浦を目指します。伊勢神宮の式年遷宮に参拝するためにです。
蛤のふたみにわかれ行秋ぞ
貝殻がふたつに別れる「二身」と「二見が浦」という地名の「二見」を掛け、さらに千住で出発の時に詠んだ「行く春や鳥泣き魚の目は泪」と対になっているわけです。
その後の松尾芭蕉
『おくのほそ道』の旅の後の芭蕉について、簡単にふれておきます。
伊勢の式年遷宮に参拝した後、故郷伊賀上野に戻り、さらに年内に
京都に出て大津、膳所をまわります。大津膳所の木曾義仲の墓のある義仲寺を拠点として、近江の門人たちに俳諧を教える生活が以後、三年ほど続きます。
芭蕉は近江の人柄と風土をよほど気に入ったようで、深川についで長く、琵琶湖湖畔にとどまっています。
その間、膳所の義仲寺を拠点として石山寺の近くの幻住庵という庵に住んだりしました。そばには紫式部が『源氏物語』の着想を得たという石山寺があります。
石山の石にたばしる霰かな
また嵯峨野の落柿舎という向井去来の住居に住まわせてもらい、嵯峨野を散歩してまわるのもの楽しいことでした。
あるいは堅田まで舟で弟子たちと出かけて、有名な浮御堂で月見を楽しんだりしました。
鎖(じょう)あけて月さしいれよ浮御堂
芭蕉は近江の人と空気がよほど気に入ったようです。深川についで長く滞在しています。
行く春を近江の人と惜しみけり
この句には、芭蕉の近江の地に対する、近江の人に対する愛情があふれています。
3年後、江戸に戻りますが芭蕉庵は人に売ってしまって無いのでした。しばらく人の家に居候していましたが、杉山杉風を中心に弟子たちがカンパしてくれて、もとあった芭蕉庵のそばに庵を再建しました。
江戸に2年暮らすうちには体がだいぶ弱まってきましたが、大坂の門人たちが仲たがいをしているということで、仲裁のために大坂に向かうことになりました。
弟子たちは、あるいは品川まで、あるいは川崎まで涙ながらに見送りました。
「先生、お体に気をつけてくださいね」
「もう奥州に行った時と同じ体ではないんですから」
「わかってる、わかってるよ…」
実際、『おくのほそ道』の旅をした時のはずんだ足取りはありませんでした。一足ごとに、体の弱まっているのが実感されました。
麦の穂を力につかむ別れかな
ふたたび大津や膳所、堅田をまわり、次に故郷伊賀上野に墓参りのために里帰りしました。兄半左衛門も、ほかの家族もすっかり衰えて杖をついて白髪頭になっていました。つくづく、時の流れというものを感じる芭蕉でした。
家は皆
杖に白髪の
墓まいり
その後大坂へ向かう途中、奈良に立ち寄ります。猿沢の池のほとりを歩き、ちょうど九月九日重陽の節句だったので、寺寺を参詣してまわります。
菊の香や
奈良には古き
仏たち
そして大坂に入ります。大坂の門人たちの家に招かれ、
住吉の市、清水の茶屋・天王寺などを吟行しますが、
秋の風は冷たく、体にしみ、芭蕉の句もいよいよ寂しさを帯びてきます。
この道や行く人なしに秋の暮れ
秋深し隣は何をする人ぞ
ついに下痢をして、どうにも動けなくなり大坂御堂前の花屋仁衛門の裏屋敷を借りて横になりました。
しかし体調は回復せず、芭蕉は弟子に筆を取らせると、「病中吟」とまず書いて、
旅に病んで
夢は枯野を
かけめぐる
と書きました。これが実質的な辞世の句となりました。
元禄7年10月12日、51歳でした。
遺骸は「木曽義仲公の墓の横におさめよ」との遺言どおり、大坂から淀川を運び、伏見で陸揚げしたあと山を越えて膳所まではこび、義仲寺で埋葬されました。
芭蕉が心から愛し、深川についで長く滞在した大津膳所の地に、親愛する木曽義仲の墓の横に、芭蕉の墓は今も立っています。