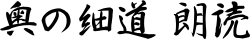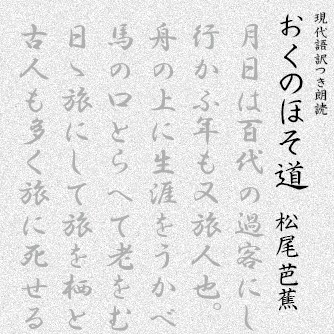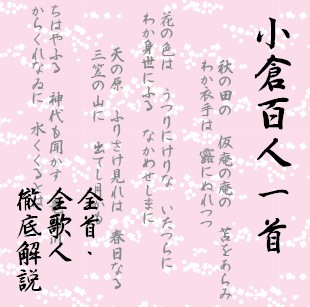山中
■『おくのほそ道』の全現代語訳はこちら
【無料配信中】福沢諭吉の生涯
■【古典・歴史】YOUTUBEチャンネル
温泉に浴す。其功有明に次と云。
山中や菊はたおらぬ湯の匂
あるじとする物は、久米之助(くめのすけ)とて、いまだ小童(しょうどう)也(なり)。かれが父俳諧を好み、洛(らく)の貞室(ていしつ)、若輩のむかし、爰(ここ)に来りし比(ころ)、風雅に辱しめられて、洛に帰て貞徳(ていとく)の門人となつて世にしらる。功名の後、此一村(このいっそん)判詞(はんじ)の料(りょう)を請ずと云(いう)。今更むかし語とはなりぬ。
曾良は腹を病て、伊勢の国長島と云(いう)所にゆかりあれば、先立て行に、
行ゝて(ゆきゆきて)たふれ伏とも萩の原 曾良
と書置たり。行ものゝ悲しみ、残るものゝうらみ、隻鳧(せきふ)のわかれて雲にまよふがごとし。予も又、
今日よりや書付消さん笠の露
現代語訳
山中温泉に入る。その効用は、有馬温泉に次ぐという。
山中や菊はたおらぬ湯の匂
(意味)菊の露を飲んで七百歳まで生きたという菊児童の伝説があるが、ここ山中では菊の力によらずとも、この湯の香りを吸っていると十分に長寿のききめがありそうだ。
主人にあたるものは久米之助といって、いまだ少年である。その父は俳諧をたしなむ人だ。
京都の安原貞室がまだ若い頃、ここに来た時俳諧の席で恥をかいたことがある。貞室はその経験をばねにして、京都に帰って松永貞徳に入門し、ついには世に知られる立派な俳諧師となった。
名声が上がった後も、貞室は(自分を奮起させてくれたこの地に感謝して)俳諧の添削料を受けなかったという。こんな話ももう昔のこととなってしまった。
曾良は腹をわずらって、伊勢の長島というところに親戚がいるので、そこを頼って一足先に出発した。
行行てたふれ伏とも萩の原 曾良
(意味)このまま行けるところまで行って、最期は萩の原で倒れ、旅の途上で死のう。それくらいの、旅にかける志である。
行く者の悲しみ、残る者の無念さ、二羽で飛んでいた鳥が離れ離れになって、雲の間に行き先を失うようなものである。私も句を詠んだ。
今日よりや書付消さん笠の露
(意味)ずっと旅を続けてきた曾良とはここで別れ、これからは一人道を行くことになる。笠に書いた「同行二人」の字も消すことにしよう。笠にかかる露は秋の露か、それとも私の涙か。
語句
■山中温泉 現石川県加賀市。 ■其功有明に次 有馬の間違い。有馬温泉は兵庫県神戸市北区にある日本三古湯の一つ。「枕草子」にも記述がある。「有馬山猪名の笹原風吹けばいでそよ人を忘れやはする」(大弐三位・後拾遺和歌集・百人一首58)■山中や… 中国河南省のレキ県にある菊の花からしたたる露を飲めば長寿を得られるという伝説に基づく。謡曲『菊慈童』は、菊の露の力で700年の長寿を保つ童を、魏の文帝(曹丕)の勅命で探索しにいく話。 ■久米之助 山中の温泉宿、泉屋甚左衛門の幼名。芭蕉来訪時14歳。この時入門し、桃夭(とうよう)の俳号を授7けられる。 ■かれが父 又兵衛豊連。寛文7年(1679年)没。つまり芭蕉が訪れた10年前に没している。『曾良旅日記』には「祖父」とある。■貞室 安原貞室(1610-73)。名は正明(まさあきら)、通称は鎰屋(かぎや)彦左衛門。寛永2年(1625年)、松永貞徳に俳諧を学ぶ。後に二代目貞徳を名乗る。 ■貞徳 松永貞徳(1571-1654)京都の人。俳人・歌人・歌学者。貞門派俳諧の祖。 ■判詞の料 俳諧の添削批評の代金。 ■長嶋 現三重県桑名郡桑名町。曾良の親戚がいた。 ■隻鳧のわかれて 「雙」で「二羽の鳥」。「隹」が一つしかない「隻」は「一羽の鳥」の意。「鳧」は千鳥に似た鳥。中国前漢の時代、蘇武とその友人李陵が匈奴に捕らわれたのに、蘇武だけが解放されることとなった。その際、蘇武が李陵に送った詩「李陵初詩」に「雙鳧ともに北に飛び、一鳧ひとり南に翔ける」ある。中島敦「李陵」、平家物語「蘇武」参照。 ■書付 巡礼者が笠に書く「乾坤無住同行二人」の文字。本来は自分と仏のことを指すが、自分と曾良のことに転じている。芭蕉は『笈の小文』の旅でも同行者杜国(万菊丸)と笠に「乾坤無住同行二人」を書いた。
解説
7月27日。芭蕉らは小松の諏訪神社の祭りを見学し、午前9時頃、山中温泉へ向けて出発しました。引き留める地元の俳人たちを泣く泣く振り切っての出発でした。
それは曾良が腹を痛めていたため、山中温泉で養生させようとしたからでした。
大丈夫かい曾良。もう少しの辛抱だぞ。先生、御心配なく…あいてて。なんて道中のやり取りも浮かびます。芭蕉、曾良のほか金沢から同行している北枝も一緒です。
途中、再度多太神社に立寄り、実盛供養の句を奉納しました。曾良と北枝も芭蕉にしたがって奉納しました。
午後五時ごろ、山中温泉到着。
『おくのほそ道』では途中那谷寺に立ち寄ったことになっていますが、『曾良随行日記』では小松→山中温泉→那谷寺の順で、こちらが実際の旅の順序と思われます。『おくのほそ道』は構成上、順序を入れ替えているようです。
山中温泉は奈良時代、僧行基が発見したと伝えられます。総湯(共同湯)である菊の湯を中心に、大聖寺川(だいしょうじがわ)渓谷沿いに多くの旅館が立ち並びます。
その後すたれますが、文治元年(1185年)源頼朝から能登国の地頭に任じられた長谷部信連が、この地で一羽の傷ついた白鷺が湯あみしているのを見て、アッ温泉だということで再興したと伝えられます。
長谷部信連というと…
『平家物語』で大活躍をする人物です。以仁王が打倒平家の令旨を発した時、平家一門にすぐにそれがバレます。
六波羅から討手が差し向けられた際、殿下お逃げくださいと以仁王を女装して逃がし、自分は三条高倉の館に踏みとどまって、我こそは長谷部信連。命を惜しまぬ者はかかってまいれ。平家方を相手に、八面六臂の戦いをしました。
しかし多勢に無勢。ついに捕えられ、ふつうなら死罪になるところ、堂々たる態度で弁明したので平家一門の人々これぞ武士の鏡よとひざを打ち、軽い罪で許されたということです。後に、源頼朝に随うこととなりました。
そんな武勇の誉高い人物が、温泉の歴史にかかわっているというのも、面白いですね。
芭蕉らが宿にした泉屋は山中温泉草創期から温泉を営む12件のうちの一件で、主人の泉屋久米之助は当時14歳という若さでした。この時入門し、桃夭(とうよう)の俳号を授けられています。
山中や菊はたおらぬ湯の匂
菊慈童の伝説に基づく句です。古代中国に菊の花びらの露を飲んで、800年の長寿をたもっている子供の話です。しかしここ山中温泉では、菊を手折るまでもなく、温泉の湯気にあたっているだけで長寿をたもてそうな気がするよ、という句です。
芭蕉らは、久米之助から、その父泉屋又兵衛にまつわる思い出話をきかされます。久米之介の父は俳諧をたしなみ、かつてここ山中温泉にまだ名が知られる前の俳諧師・安原貞室が来たことがありました。
その時安原貞室は何も勉強をしておらず、俳諧の席でぶざまな句を詠んで大恥をかいてしまいました。
「ダメですねえ貴方。もっと勉強しましょうよ」
「くっ…勉強ですか」
こうして一念発起した安原貞室は、京都にのぼって有名な松永貞徳の弟子となり、古典の勉強をして俳諧の素養を身につけ、立派な俳諧師となったということです。
後にふたふたび山中温泉を訪れた俳諧師安原貞室は、この地で俳諧の席を持ちましたが、当然受け取るべき添削料を受け取りませんでした。自分を一念発起させてくれたこの山中の地に敬意を表してです。
ここ山中の地で恥をかくことがなければ、今の私はなかった。出発点だ。原点だ。ありがとうというわけです。
「なるほど…そんな昔もあったのですね」
ズズ…茶をすすりながら、宿の主人と盛り上がっていると、曾良が腹を抱えていました。
「おい、どうした曾良」
「いてて、いよいよ腹の調子が悪いみたいです」
「なに温泉でもダメか…」
どうにも腹がよくならないので、曾良は一足先に伊勢の長島に親戚がいるので、そこを頼って一足先に出発することになりました。
「では先生、お先に」
「おう、気をつけてな」
「よっと…旅立ちにあたって、一句詠んでおきましょう」
行き行きて倒れ伏すとも萩の原
このままどこまでも行って、萩の原で旅の途上で死のう。
「おお…思い切った句を詠んだものだなあ」
ここまで旅に同行してくれた曾良に対する感謝、愛着があらためて沸き起こります。
思えばよくぞついてきてくれたものです。深川を出て以来の楽しかった場面、ひどい目にあったこと、泣き笑いの数々が芭蕉の脳裏によぎります。
芭蕉と曾良の笠の裏側には、「乾坤無住同行二人」と記してありました。天地にお前と私、二人だけだという意味です。もともと仏さまと私のことを言っていますが、芭蕉は自分と曾良のこととして考えていました。
しかし、ずっと共に旅を続けてきた曾良ともここで別れ別れになってしまうわけです。
「この文字も…いったん消してしまおう」
芭蕉は笠についた露で文字を消しました。
今日よりや書付消さん笠の露
芭蕉の曾良に対する深い愛情が伝わってくる句です。