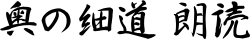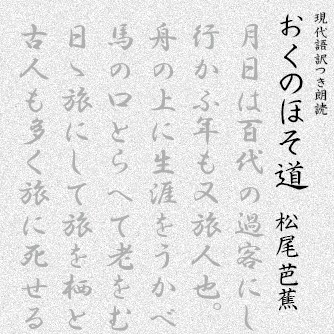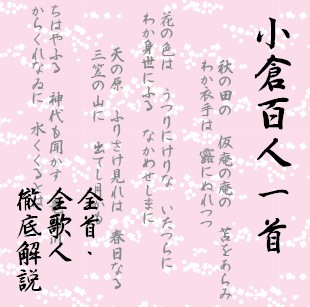白河の関
■『おくのほそ道』の全現代語訳はこちら
■【古典・歴史】メールマガジン
■【古典・歴史】YOUTUBEチャンネル
心許なき日かず重るまゝに、白川の関にかゝりて旅心定りぬ。「いかで都へ」と便求しも断也。中にも此関は三関の一にして、風【馬+「操」の右】の人心をとゞむ。秋風を耳に残し、紅葉を俤にして、青葉の梢猶あはれ也。卯の花の白妙に、茨の花の咲そひて、雪にもこゆる心地ぞする。古人冠を正し衣装を改し事など、清輔の筆にもとゞめ置れしとぞ。
卯の花をかざしに関の晴着かな 曾良
現代語訳
最初は旅といっても実感がわかない日々が続いたが、白河の関にかかる頃になってようやく旅の途上にあるという実感が湧いてきた。
平兼盛は「いかで都へ」と、この関を越えた感動をなんとか都に伝えたいものだ、という意味の歌を残しているが、なるほどもっともだと思う。
特にこの白河の関は東国三関の一つで、西行法師など、昔から風流を愛する人々の心をとらえてきた。
能因法師の「都をば霞とともにたちしかど秋風ぞ吹く白川の関」という歌を思うと季節は初夏だが、秋風が耳奥で響くように感じる。
また源頼政の「都にはまだ青葉にて見しかども紅葉散りしく白河の関」を思うと青葉の梢のむこうに紅葉の見事さまで想像されて、いっそう風雅に思えるのだった。
真っ白い卯の花に、ところどころ茨の白い花が咲き混じっており、雪よりも白い感じがするのだ。
陸奥守竹田大夫国行が白河の関を越えるのに能因法師の歌に敬意を払って冠と衣装を着替えて超えたという話を藤原清輔が書き残しているほどだ。
卯の花をかざしに関の晴着かな 曾良
(かつてこの白河の関を通る時、陸奥守竹田大夫国行(むつのかみたけだのだいふくにゆき)は能因法師の歌に敬意を表して 衣装を着替えたという。私たちはそこまではできないがせめて卯の花を頭上にかざして、敬意をあらわそう)
語句
■白川の関 白河の関。『奥の細道』冒頭にも「白河の関越えんと」と記されているとおり、旅の主要な目的地の一つであった。現福島県白河市。奥羽三関の一つ。ほかは常陸の勿来関、羽前の念珠関。五世紀ごろ、蝦夷の南下を防ぐ砦として作られた。能因法師の歌で有名となる。西行法師、一遍、宗祇などが訪れる。八世紀には廃止。江戸時代、正確な位置は不明だった。 ■いかでみやこへ 「便りあらばいかで都へ告げやらむけふ白河の関は越えぬと」(拾遺集・別 平兼盛)(つてがあったら、なんとか都へ報告したい。今日白河の関を越えたと)。 ■三関 奥羽三関。常陸の勿来関、羽前の念珠関。陸奥の白河関。 ■風【馬+「操」の右】の人 「風騒」。風流を愛する人。詩歌・文章を作る人。 ■心をとどむ 「白河の関屋を月のもるかげは人の心をとむるなりけり」(新拾遺・羇旅、山家集下 西行) ■秋風を耳にのこし 「都をば霞とともにたちしかど秋風ぞ吹く白川の関」(後拾遺・羇旅 能因法師)。 ■もみぢを俤にして 「都にはまだ青葉にて見しかども紅葉散りしく白河の関」(千載・秋下 源頼政)。 ■雪にもこゆる 「別れにし都の秋の日数さへつもれば雪の白川の関」(続拾遺・冬 大江貞重) ■古人冠をだゞし 「竹田大夫国行と伝者、陸奥国に下向の時、白川の関すぐる日は、殊に装束ひきつくろひむかふと云々。人問て伝く、何等の故ぞ哉。答て伝く、古曾部の入道の、秋風ぞふく白河の関と読れたる所をば、いかでかけなりにては過ぎんと伝々」(袋草紙・巻三)。 ■清輔 藤原清輔(1104-1177)。平安時代末期の公家・歌人。父は左京大夫藤原顕輔。崇徳上皇より父顕輔は『詞歌和歌集』の編纂を命じられ、清輔も補助にあたる。後、二代の后藤原多子に仕えた。『袋草紙』の作者。百人一首に「長らへばまたこの頃やしのばれむうしと見し世ぞ今は恋しき」が採られる。
解説
白河の関は『奥の細道』冒頭にも「白河の関越えんと」と書かれているとおり、『奥の細道』の主要な目的地の一つでした。
白河の関には平兼盛、能因法師、源頼政…昔から多くの文人墨客が訪れ、歌を詠みました。
芭蕉は彼らの歌の文句を織り込みながら、華麗な文体で語っていきます。
ようやく白河の関を実際に見ることができた。ああ、私は今長い歴史の上に立っている…その感動が伝わってくる章です。
この章のポイントは、初夏の景色のむこうに秋の景色を見ているということです。古くから、白河の関といえば秋でした。
能因法師が詠みました。「都をば霞とともにたちしかど秋風ぞ吹く白川の関」、源頼政が詠みました。「都にはまだ青葉にて見しかども紅葉散りしく白河の関」などです。
しかし芭蕉が訪れたの初夏。真っ白い卯の花が咲き乱れ、秋の景色とはまるで違うのですが、芭蕉は目の前の初夏の白河の関の景色の向うに、古典に描かれた秋の白河の関をイメージしているわけです。
かつて、能因法師は白河の関で「都をば霞とともにたちしかど秋風ぞ吹く白川の関」と詠みました。もっとも都にいながら想像だけでこの歌を詠んだという説もありますが。
その能因法師の故事に敬意を表して、竹田大夫国行という人が白河の関を越える時には衣装を着替えて、正装して通ったといいます。
こういう歴史をふまえての曾良の句です。「卯の花をかざしに関の晴れ着かな」…私たちはまさか衣装を着替えて通るまではできませんが、せめてこう卯の花をかざして、これを白河の関を通る晴れ着のかわりとしましょう。
この句は曾良のもので、芭蕉の句はありません。感激のあまり詠めなかったのかもしれませんが、クライマックスになると句が出てこないのは芭蕉の紀行文では毎回の定石です(『鹿島詣』でようやく当初の目的であった鹿島の月を見たのに感激のあまり句が出ない。『笈の小文』で花の吉野に来て感激のあまり句ができないなど)。