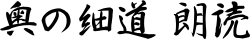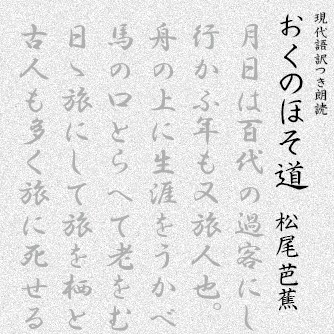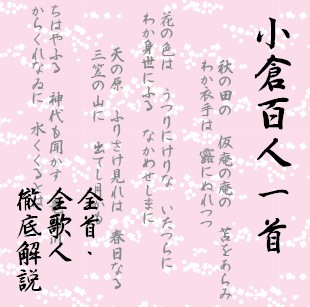黒羽
■『おくのほそ道』の全現代語訳はこちら
■【古典・歴史】メールマガジン
■【古典・歴史】YOUTUBEチャンネル
黒羽の館代浄坊寺何がしの方に
音信 る。思ひがけぬあるじの悦び、日夜語りつゞけて、其弟桃翠など云が、朝夕勤とぶらひ、自の家にも伴ひて、親属の方にもまねかれ、日をふるまゝに、ひとひ郊外に逍遥して、犬追物の跡を一見し、那須の篠原をわけて、玉藻の前の古墳をとふ。それより八幡宮に詣。与市扇の的を射し時、「別しては我国の氏神正八まん」とちかひしも、此神社にて侍と聞ば、感応殊にしきりに覚えらる。暮れば桃翠宅に帰る。修験光明寺と云有。そこにまねかれて、行者堂を拝す。
夏山に足駄を拝む首途哉
現代語訳
黒羽藩の留守居役の家老である、浄坊寺何がしという者の館を訪問する。主人にとっては急な客人でとまどったろうが、思いのほかの歓迎をしてくれて、昼となく夜となく語り合った。
その弟である桃翠という者が朝夕にきまって訪ねてきて、自分の館にも親族の住まいにも招待してくれた。
こうして何日か過ごしていたが、ある日郊外に散歩に出かけた。昔、犬追物に使われた場所を見て、那須の篠原を掻き分けるように通りすぎ、九尾の狐として知られる玉藻の前の塚を訪ねた。
それから八幡宮に参詣した。かの那須与一が扇の的を射る時「(いろいろな神々の中でも特に)わが国那須の氏神である正八幡さまに(お願いします)」と誓ったのはこの神社だときいて、神のありがたさもいっそう身に染みて感じられるのだった。
日が暮れると、再び桃翠宅に戻る。
近所に修験光明寺という寺があった。そこに招かれて、修験道の開祖、役小角(えんのおづぬ)をまつってある行者堂を拝んだ。
夏山に足駄を拝む首途哉
役小角(えんのおづぬ)のお堂を拝む。この夏山を越せばもう奥州だ。小角が高下駄をはいて山道を下ったというその健脚にあやかりたいと願いつつ、次なる門出の気持ちを固めるのだ。
語句
■黒羽 栃木県那須郡黒羽町。芭蕉は黒羽に『おくのほそ道』中最長の14日間滞在した。 ■館代 城代家老。黒羽には城が無く館だったので「館代」と呼んだ。 ■浄坊寺何がし
解説
那須の黒羽では、『曾良旅日記』によると二週間も滞在しています。「尾花沢」に次いで長い滞在です。
芭蕉はここ黒羽で、黒羽藩城代家老浄坊寺図書高勝に招かれ、その弟桃翠という者の歓迎を受けます。実際の名は翠桃だったとわかっていますが、『おくのほそ道』作中では漢字がひっくり返っています。
あくまで作中人物だ。創作物だということであえてひっくり返したと思われます。よく漫画で「SONY」が「SOMY」になってますよね。あんな感じだと思われます。もっとも単なる間違いの可能性もありますが。
芭蕉は桃翠の案内で黒羽の名所を訪ねてまわります。まず「犬追物の跡」。「犬追物」はは鎌倉時代に盛んだった競技で、囲いの中に150匹の犬を放って36人馬上から射て何匹射たかを競いました。流鏑馬・笠懸と並び騎射三物(きしゃみつもの)の一つとされます。
ただし実際に射殺すのではなく「蟇目の矢」という特殊な鏑矢で射ました。また、次の「九尾の狐」を那須の地に三浦義明・千葉常胤・上総広常らが追い詰めたことも「犬追物」といいます。
そして「玉藻の前の古墳」。「玉藻の前」は鳥羽上皇の寵愛を受けていた美女ですが、その正体は毛が金色で九の尾を持つ「九尾の狐」でした。
陰陽師阿部康成によって正体をあばかれると九尾の狐は宮廷を逃げ出しますが、三浦義明、千葉常胤、上総広常ら討伐軍に追い詰められ、那須野で射殺されました。その霊は殺生石と化し近づく人々を毒にあてて殺したといいます。
そして那須余一が八島の合戦で第一に祈った八幡宮。。那須与一は扇の的を射抜くため海岸に馬を乗り出した時、波風が立って的を射抜くのが難しいと見て故郷那須の神々に祈っりました。
「南無八幡大菩薩、別しては我が国の神明、日光の権現、宇都宮、那須の湯泉大名神、願はくはあの扇の真中射させてたばせ給へ。これを射そんずる物ならば、弓きりをり自害して、人にニたび面をむかふべからず。いま一度本国へむかへんとおぼしめさば、この矢はづさせ給ふな」と。
芭蕉はその八幡宮を訪ねて、しきりに感激しています。
また修験光明寺という寺を訪ねます。この寺のお堂には役行者の像を祀ってあります。「役小角」は飛鳥時代から奈良時代にかけて大和葛城山を中心に活躍した伝説的な呪術者です。藤原鎌足の病を治した伝説が知られています。師の能力をねたんだ弟子の密告により伊豆大島に流されたといいます。
絵に描かれた役行者は多く高下駄をはいています。トレードマークとも言うべきものです。それで、芭蕉は役行者の健脚にあやかろうと、役行者像の高下駄に祈りました。「夏山に足駄を拝む門出かな」と。