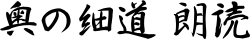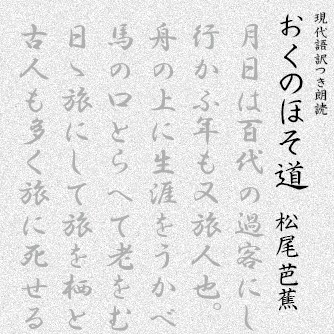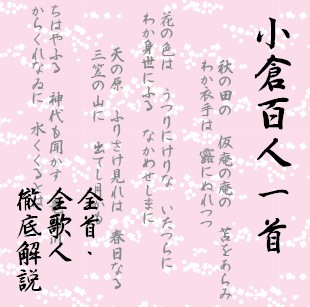『奥の細道』について
■『おくのほそ道』の全現代語訳はこちら
■【古典・歴史】メールマガジン
■【古典・歴史】YOUTUBEチャンネル
元禄ニ年、四十六歳の松尾芭蕉は門人河合曾良と共に『奥の細道』の旅へ出発します。深川の庵を出発し奥羽、北陸を経て美濃の大垣まで全行程約600里(2400キロメートル)、日数約150日間にわたる壮大な旅です。それは西行、能因といった過去の文人たちの魂に触れる旅であり、ロマン溢れる歌枕の地を訪ねる旅でした。
「おくのほそ道」は、この旅を下敷きに文学的虚構を加え構成に工夫を凝らし、五年の歳月を経て完成され、芭蕉の死後の元禄15年(1702年)京都の井筒屋から刊行されました。紀行文学の代表作といわれます。
松島、平泉、象潟の三箇所は特に主要な旅の目的地であり、それぞれ文体に工夫を凝らし語られています。
「おくのほそ道」という題は、「壷の碑(つぼのいしぶみ)」の章に見える、塩釜街道の名から取られています(本文中で「おくの細道」という単語が使われるのはここだけ)。
芭蕉は新しい紀行文を書くにあたって、それまでと同じことをしても意味がないと考えました。「奥の細道」以前の紀行文として紀貫之「土佐日記」、鴨長明?「東関日記」、阿仏尼「十六夜日記」などがありますが、芭蕉は「笈の小文」の中でこれらに勝るものは書けないと述べています。よってこれらにかわる「新しさ」が必要だと。
まず実際の旅をそのまま記すのではなく事実の再構成、文学的脚色を意識的に行っています。比較的事実そのままに記されているとされる「曾良旅日記」と比較すると、その工夫のこらし方がハッキリします。
例えば日光への到着をドラマチックに演出するために敢えて日付をずらす、「松島」と「象潟」を対照的に扱いコントラストを強調する、「市振」のような完全に創作の章を加える…といった具合です。
「仏五左衛門」「市振」「等栽」など、人物を主体とした章を設けたのも、「奥の細道」以前の紀行文では珍しいことでした。
芭蕉は「奥の細道」の旅を通し「不易流行」の考えを得ました(「不易」…永遠に変わらない本質的なもの、「流行」…時代とともに移り行くもの。時々の流行。この二つは元は一つ(風雅の誠)とする考え。ただしこの単語は「奥の細道」の中には無い)。
また、「かるみ」の境地に達しました。「かるみ」とは、苦しみ悩みに満ちた世の中を、それでも微笑みながら生きていこうという考えです。『おくのほそ道』の旅の後の芭蕉の句には、しだいに「かるみ」の傾向があらわれてきます。